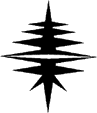| 秦荘町の歴史は古く、各所に集落遺跡等が発見されています。常安寺遺跡、金剛寺野遺跡等の古墳群があって、石器や土器を出土しています。大化の改新によって中央集権的な国家体制が始まり、当地域は蚊野郷、八木郷に属し条里制が施行され「一ノ坪、四ノ坪、十八、十九」などの小字名を残しています。また、白鳳時代の寺院瓦が発見されています。秦川山の西麓に位置する湖東三山で知られる金剛輪寺は聖武天皇勅願により天平13年(741年)に行基菩薩が開山した古い寺院であり、室町時代に全盛期を迎えました。金剛輪寺は、この地域に勢力をもっていた秦氏一族の崇敬を得ていました。荘園の地頭に目加田氏、安孫子氏、狩野氏等の名を残し、中世になると織田信長が近江に入ってきて、当地方を掌握した。信長の死後、秀吉の直轄領となっていた。江戸期は、金剛輪寺領となった松尾寺村30石のほか全て彦根藩井伊家の所領となりました。明治4年の廃藩置県後、大区小区制、郡区町村編成、連合戸長役場制等により管轄区域の変更がありましたが同22年町村制施行により秦川、八木荘の2村が成立し、以後66年間行政区画の変更を見ることもなくそれぞれ地方自治体としてのあゆみを続け、昭和30年4月、この2村が合併し、現在の秦荘町が誕生しました。 |
|
| 愛知川町は弥生時代の前期・後期の土器片が多く出土しており、早くから開けた地域です。田園部には大化の改新の前後に成立したといわれる条里制の遺構が多く残されています。荘園時代には愛知川町を含む一帯は大国荘と呼ばれており、その氏神が今も豊満陣神社に残っています。古くから交通の要衝の地に有り、東山道の宿駅が設けられていましたが、中世後期にはすでに近江の主要八駅のひとつとして愛知川の名は広く知られていました。その後彦根藩井伊氏の封地となった近世には、問屋が三軒、旅館が数十件あり、中山道66番目の宿場町「愛知川宿」として栄えてきました。明治12年以後は、郡役所、警察などの官公署が設立され郡の首邑として繁栄。明治31年に近江鉄道が開通し、町はこの地方の中心都市として発展しました。明治30年代には戸数1000有戸余、人口6000人を超え、人口密度も1k㎡当たり700人となり、郡役所をはじめ多くの官公署や商家を有して、町としての機能を備えており、明治42年10月県下14番目の町として愛知川町が成立しました。昭和28年公布の町村合併促進法により、愛知川町と豊国村が同30年に合併し、現在の愛知川町が誕生しました。その後、恵まれた立地条件を生かし企業誘致に力を入れ、優良企業が立地し、活力とうるおいのあるまちづくりに力を入れています。 |
|