負担を軽減するための制度
介護保険のサービスを利用するには自己負担(かかった費用の1割)が必要ですが、利用者負担段階別に一定の条件を満たした人の利用の負担が大きくなった場合には、負担を軽減する制度があります。いずれも申請が必要です。
高額介護(介護予防)サービス費
対象者
同じ月に利用したサービスの利用者負担額の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額)が高額になり、一定額(上限額)を超えたときは、申請によって超えた金額を「高額介護(介護予防)サービス費」としてあとから支給されます。
(令和3年8月より変更)
生活保護受給者
利用者負担の上限額(月額)
(個人)15,000円
(世帯)15,000円
世帯全員が住民税非課税
利用者負担の上限額(月額)
(個人)15,000円
- 老齢福祉年金受給者
- 合計所得額と課税年金収入の合計が80万円以下の方など
利用者負担の上限額(月額)
(世帯)24,600円
- 合計所得額と課税年金収入の合計が80万円を超える方など
住民税課税世帯で下記3区分に該当しない人
利用者負担の上限額(月額)
(世帯)44,000円
3年間の時限措置として、同じ世帯の65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限:446,400円を設定。
現役並み所得者
利用者負担の上限額(月額)
(世帯)44,000円
- 同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の年収が単身380万円未満
利用者負担の上限額(月額)
(世帯)93,000円
- 同一世帯に課税所得380万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の年収が単身690万円未満
利用者負担の上限額(月額)
(世帯)140,100円
- 同一世帯に課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる世帯
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は、合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれ月の限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して下表の限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の利用者負担限度額(年額/8月~翌年7月)
| 所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満の人 |
|---|---|
| 901万円超 | 212万円 |
| 600万円超901万円以下 | 141万円 |
| 210万円超600万円以下 | 67万円 |
| 210万円以下 | 60万円 |
| 住民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 70~74歳の人 | 後期高齢者医療制度 で医療を受ける人 |
|---|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 212万円 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上 | 141万円 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上 | 67万円 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 | 56万円 |
| 低所得者(2) | 31万円 | 31万円 |
| 低所得者(1) | 19万円 | 19万円 |
低所得者(1)区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法がことなります。
- 毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。
- 支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。
負担限度額の認定
制度概要
介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設(療養病床等)、介護医療院やショートステイを利用している方の食費・居住費(滞在費)の限度額を定める負担限度額認定については以下のとおりです。
利用者負担の限度額(日額)
以下の表の(A)(B)両方に該当していると認められた場合、特定入所者介護(予防)サービス費が支給され、居住費等、食費が負担限度額まで軽減されます。

※介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、()内の金額です。
※世帯や夫婦には世帯分離している配偶者や事実上の婚姻関係にある場合も含みます。
※第2号被保険者(40~64歳の医療保険加入者)の預貯金等の額は、上記にかかわらず単身1,000万円、夫婦2,000万円以下の場合となります。
申請に必要なもの
| 必要書類 | 詳細 |
| 対象者の全ての預貯金額がわかるもの |
|
| 配偶者の全ての預貯金額がわかるもの | 同上 |
その他
- 預貯金等の出金・解約等の履歴に疑義が生じた場合は、調査を行いますので領収書等を提出いただきます
- 認定となる場合は申請日の属する月の初日(1日)に遡ります。(申請月以前の遡りは行えません)
- 提出書類に不備はある場合は申請を行えませんので、必要書類を全て揃えたうえで申請を行ってください
- 認定後に預金額の基準額超過または、所得の更正等により課税世帯に変更になった場合は速やかに福祉課にご連絡ください。なお、認定対象外となった月の翌月分から介護給付を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還いただくことがあります
社会福祉法人などによる利用者負担軽減制度
対象者
世帯全員が市町村民税非課税であって、次の全てに該当する方です。
- 世帯の年間収入が基準収入額以下の方。
(基準収入額とは、ひとり世帯の場合150万円、世帯構成員が1人増える毎に50万円を加えた額) - 世帯の預貯金額が基準貯蓄額以下の方。
(基準貯蓄額とは、ひとり世帯の場合350万円、世帯構成員が1人増える毎に100万円を加えた額) - 世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない。
- 負担能力のある親族などに扶養されていない方。(医療保険などの扶養になっていない。)
- 介護保険料を滞納していない方。
なお、生活保護受給者および旧措置入所者で利用負担割合が5%以下の者については、軽減の対象となりません。
内容
利用者負担軽減の申出のあった社会福祉法人などで次の介護(介護予防)サービスの提供を受けられた場合に利用者負担額が軽減(2分の1もしくは4分の1)されます。
訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護予防訪問介護・介護予防通所介護・介護予防短期入所生活介護・指定介護老人福祉施設における施設サービス費・日常生活に要する食費および居住費(滞在費)
お問合せ先
- 介護保険に関すること
福祉課(愛知川庁舎)電話番号0749-42-7691 - 総合相談・介護予防に関すること
地域包括支援センター(愛知川庁舎)電話番号0749-42-4690
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7691
ファックス:0749-42-5887
メールフォームによるお問い合わせ
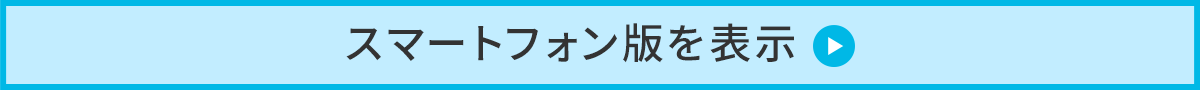





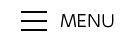



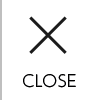
更新日:2021年08月01日