課税の改正点
令和7年度個人住民税の主な改正点
1.令和7年度個人住民税の特別税額控除(定額減税)
2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充・延長
3.国外に居住する親族等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し
1.令和7年度個人住民税の特別税額控除(定額減税)
令和7年度の個人住民税においては、令和6年の納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超えて、1,805万円以下であり、かつ控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)を有する納税義務者に対して特別税額控除(定額減税)を実施します。
令和7年度個人住民税の定額減税額は1万円です。ただし、定額減税額が個人住民税所得割額を超える場合は、個人住民税所得割額が限度額となります。
2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)
子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
令和6年度税制改正により、子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合に、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。

新築住宅の床面積要件の緩和
合計所得金額1,000万円以下の方に限り、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置について建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。(改正前:令和5年12月31日)
ただ、令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除を受けられません。

(国土交通省HPから引用)
3.国外に居住する親族等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し
国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。
令和6年度個人住民税の主な改正点
1.森林環境税の導入
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
4.定額減税の実施
1.森林環境税の導入
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境贈与税が創設されました。
森林環境税は、令和6年度より町民税・県民税(個人住民税)の均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市区町村が賦課徴収することとされており、その税収は、全額が森林環境贈与税として市区町村や都道府県へ贈与されます。

・森林環境税 1,000円/年・人
・均等割 町民税3,000円/年・人、県民税1,800円/年・人
・県民税の均等割税率2,300円のうち、800円は琵琶湖森林づくり県民税分です。
・所得割 標準税率採用 町民税6%、県民税4%
2.上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになりました。
これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなり、所得税の確定申告で上場株式等の配当所得等および譲渡所得等を申告した場合は住民税でも同じ課税方式で計算されます。
※住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
【上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る課税方式】

3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度の住民税から、年齢30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外になります。
1.留学により国内に住所および居住を有しなくなった者
2.障害者
3.扶養控除を申告する納税義務者からその年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者
扶養控除を受ける際に提出または提示が必要な書類

注1:書類が外国語で作成されている場合は翻訳文が必要です。
注2:扶養親族が複数いる場合は各人への送金関係書類が必要です。代表者への一括送金の場合はその代表者のみが扶養対象者となります。
定額減税の実施
定額減税に関する詳細は、「個人住民税(町・県民税)の定額減税について」ページをご参照ください。
令和5年度個人住民税の主な改正点
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
2.民法改正による未成年の住民税の扱いについて
3.セルフメディケーション税制の見直し
1.住宅ローン控除の特例期間の延長
・住宅ローン控除の期間延長により、令和4年1月1日から令和7年12月31日までの間 に入居した方が対象となります。
・消費税率の引上げに伴う需要平準化対策が終了したため、控除限度額を前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)に引き下げます。
【参考】

(補足)表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。
(注1)住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、表中2の控除限度額と同じとなります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
【住宅ローン控除の控除期間】

2.民法改正による未成年の住民税の扱いについて
民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。この改正に伴い、令和5年度以降の「未成年住民税課税」の対象年齢について、以下の通り変更します。そのため、昨年度までは非課税であっても、今後は課税となる場合がありますのでご注意ください。
(補足)「前年の合計所得135万円以下」は変更ありません。
【未成年の対象年齢】

3.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の適用期限が5年間延長されます。(令和8年12月31日までの間に支払った対価が対象)
令和4年度個人住民税の主な改正点
1.住宅ローン控除の特例の延長等
2.セルフメディケーション税制の見直し
3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
4.退職所得課税の適正化
1.住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間(※)に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
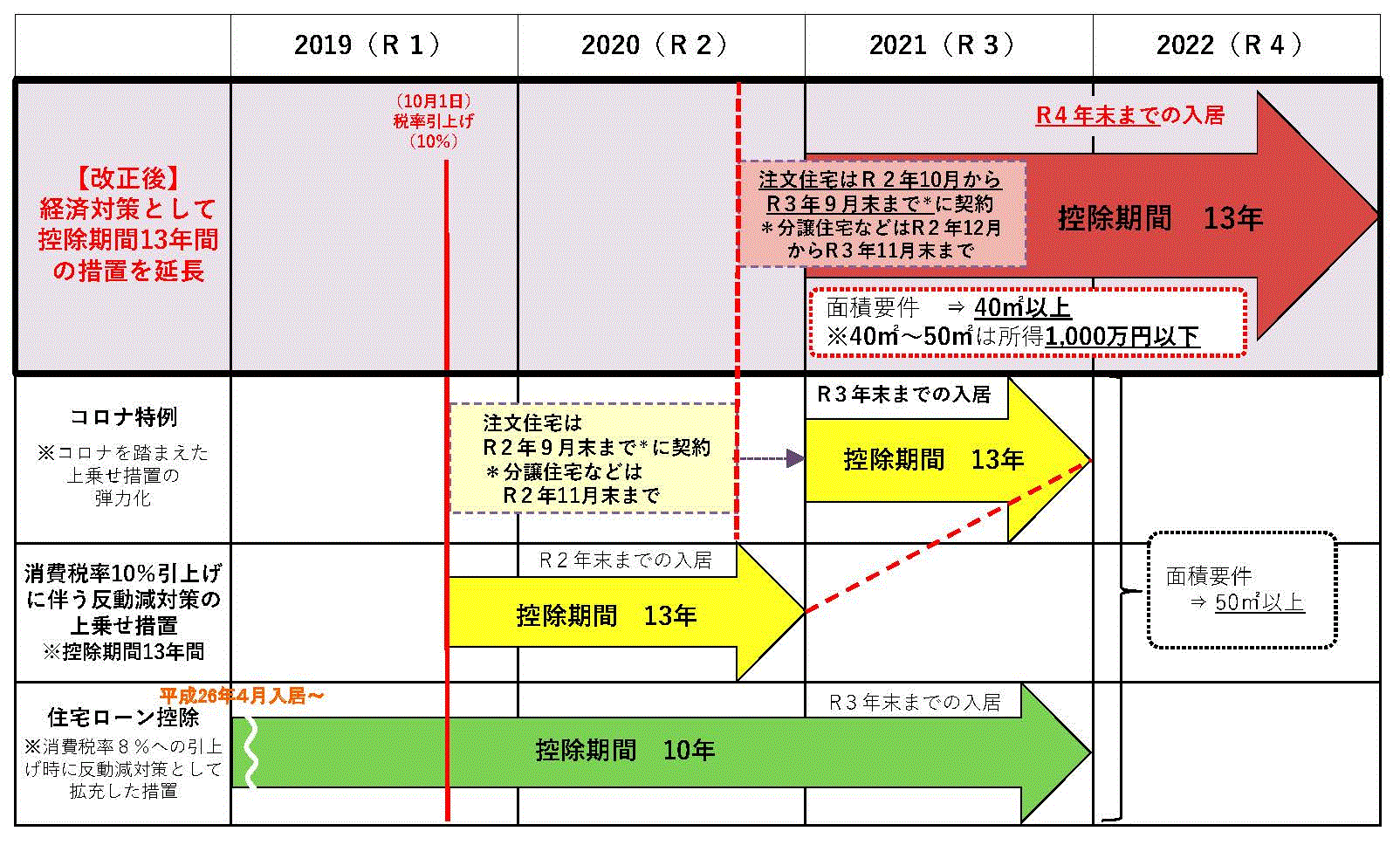
セルフメディケーション税制の見直し
対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化をしたうえで、平成29年1月1日から令和3年12月31日までだった適用期限が5年延長されます。なお、令和4年分以後から適用です。
3.国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税とします。対象範囲は、子育てに係る施設やサービスの利用料に対する助成とします。なお、令和3年分以後からの適用です。
1.ベビーシッターの利用料に対する助成
2.許可外保育施設等の利用料に対する助成
3.一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成についても対象(例:生活援助や家事支援、保育施設等の副食費や交通費等)
4.退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金についても、雇用の流動性等に配慮しながら、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分について、2分の1課税の平準化措置の適用から除外することとします。なお、令和4年分以後から適用です。
令和3年度個人住民税の主な改正点
1.給与所得控除の見直し
2.公的年金等控除の見直し
3.基礎控除の見直し
4.調整控除の見直し
5.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
1.給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、その上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられます。
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | その収入金額×40%-10万円 | その収入金額×40% |
| 180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+8万円 | その収入金額×30%+18万円 |
| 360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+44万円 | その収入金額×20%+54万円 |
| 660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+110万円 | その収入金額×10%+120万円 |
| 850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
| 1,000万円超 | 220万円 | |
(注意)給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の1から4のいずれかの要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引きます。
- 特別障害者に該当する
- 22歳以下の扶養親族を有する
- 特別障害者である同一生計配偶者を有する
- 特別障害者である扶養親族を有する
◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1
なお、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1,000万円となります。
2.公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額については、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下である場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律10万円、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円を超える場合の控除額を上記の見直し後の控除額から一律20万円、それぞれ引き下げられます。
|
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
| 改正後 | 改正前 | |||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | |
| 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
|
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 27万5千円 |
(A)×25%+ 17万5千円 |
(A)×25%+ 7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 68万5千円 |
(A)×15%+ 58万5千円 |
(A)×15%+ 48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 145万5千円 |
(A)×5%+ 135万5千円 |
(A)×5%+ 125万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
|
公的年金等の 収入金額(A) |
公的年金等控除額 | |||
| 改正後 | 改正前 | |||
| 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||||
| 1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | |
| 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
|
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+ 27万5千円 |
(A)×25%+ 17万5千円 |
(A)×25%+ 7万5千円 |
(A)×25%+37万5千円 |
|
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+ 68万5千円 |
(A)×15%+ 58万5千円 |
(A)×15%+ 48万5千円 |
(A)×15%+78万5千円 |
|
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+ 145万5千円 |
(A)×5%+ 135万5千円 |
(A)×5%+ 125万5千円 |
(A)×5%+155万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | |
給与収入と公的年金等の収入が双方にあり、それらの所得金額の合計が10万円を超える場合は給与所得の金額から、次の算式により計算した金額を控除します。
◆所得金額調整控除=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
3.基礎控除の見直し
- 基礎控除額が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える所得割の納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額となり、合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされます。
| 所得割の納税義務者の合計所得金額 | 基礎控除 | |
| 改正後 | 改正前 | |
| 2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
| 2,500万円超 | 適用なし | |
4.調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外とされます。
| 改正後 | 改正前 | ||
| 合計所得金額 | 調整控除 | 調整控除 | |
| 2,500万円以下 | 計算方法を参照 | 一律 | 計算方法を参照 |
| 2,500万円超 | 0円 | ||
計算方法
課税標準額が200万円以下の場合
下記のいずれか少ない金額×5%(町民税3%、県民税2%)
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税の課税標準額
課税標準額が200万円超の場合
{人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%
2,500円未満のときは、2,500円(町民税3%、県民税2%)
5.非課税基準、扶養親族等の合計所得金額要件等の見直し
| 要件等 | 改正後 | 改正前 | |
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
| 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
| 勤労学生の合計所得金額要件 | 75万円以下 | 65万円以下 | |
| 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
| 寡婦および寡夫に係る生計を一にする子の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
| 雑損控除に係る親族の総所得金額等要件 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
| 障害者、未成年者、寡婦および寡夫に対する個人町民税、県民税の非課税措置の合計所得金額要件 | 135万円以下 | 125万円以下 | |
|
均等割の非課税限度額の合計所得金額 (非課税となる方) |
扶養者がいない場合 | 38万円以下 | 28万円以下 |
| 扶養者がいる場合 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+26万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+16万8千円 | |
|
所得割の非課税限度額の総所得金額等 (均等割のみ課税される方) |
扶養者がいない場合 | 45万円以下 | 35万円以下 |
| 扶養者がいる場合 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+42万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円 | |
事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親の個人住民税は非課税となる新たな非課税措置が創設されます。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課
〒529-1380 滋賀県愛知郡愛荘町愛知川72番地
電話番号:0749-42-7690
ファックス:0749-42-7117
メールフォームによるお問い合わせ
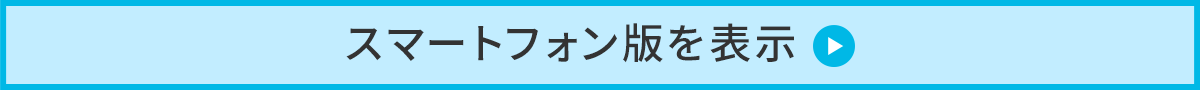





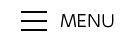



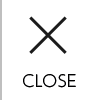
更新日:2025年04月01日